会長挨拶
日本大気化学会とは
日本大気化学会は大気化学および関連する学問分野に関心を持つ研究者相互の連携・学術交流などを通じ、当該学問分野の進歩発展を図り、基礎研究を推進するとともに、地球温暖化や大気汚染などの課題解決の鍵となる知見の創出などを通じて社会へ貢献することを 目的とした学術研究団体です。地球大気化学国際協同研究計画(IGAC)に深く関わる国際連携も推進しています。 The Japan Society of Atmospheric Chemistry (JpSAC) is an academic research organization that aims to promote basic research and to contribute to society through collaboration and academic exchange among researchers interested in atmospheric chemistry and related disciplines.
日本の大気化学を支える基盤として
日本大気化学会の会長として2025年7月に就任しました名古屋大学の持田陸宏です。皆様どうぞよろしくお願い申し上げます。
本学会は、大気化学研究会を前身として2014年に発足しました。それから10年余り、春秋2回の研究集会の開催、学会誌「大気化学研究」のオンライン発行などを通して、日本の大気化学分野の議論の場としての役割を担っています。2022~2023年には、本分野に関わる多くの方々のご尽力により、「大気化学研究」誌の総説として「大気化学の将来構想 2022-32」が発行されました。また、前期の運営委員会の下で選挙制度の見直しが行われるなど運営面の整備も進み、本学会は日本の大気化学研究を支える「持続可能」な基盤として成熟しつつあります。GOSAT-GWの衛星観測プロジェクトや北極研究プロジェクトなどの、大気化学に関わる諸々の研究活動の今後の発展が期待される中、本学会は引き続き重要な役割を担うことが期待されます。
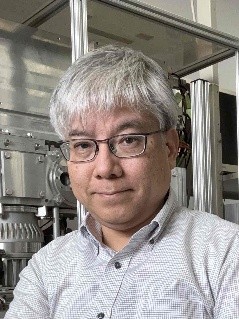
持田陸宏
本学会は、前身である研究会の当時からの、基盤となる所属学会を各々が持つ研究者の交流の場としての役割に加え、独立した学会としての取り組みを通して、大気化学分野の研究者の活動の基盤となる役割を果たすようになりました。このように基盤学会としての機能を持つに至った今、異分野の交流・連携について改めて考え、垣根を越えた学際・融合的研究の足場としての原点を振り返ることが必要ではないかと考えています。研究者の学会ごとの分断をもたらすのではなく、関連分野との協同を生み育てる場として本学会が機能することを期待し、その実現に目を向けたいと思います。
もちろん、この点に限らず、本学会に期待される役割は様々です。将来構想として論じられた各課題に関して、研究集会や学会誌は実践の成果を共有し、また、当時の構想を超えて議論を深める場を提供することが期待されます。これにより、新たな研究プロジェクトの立案や、日本の大気化学研究のインフラの整備などの本分野の課題の検討・発信の場となることも考えられます。また、若手人材の育成や多様性の確保への支援は、学会として取り組むべき優先度の高い課題であり、これまでの取り組みの維持・発展に務める必要があります。そのほか、学術研究の継続において社会からの信頼と支持がますます必要となる中、大気化学の研究活動の意義を社会でより広く知っていただく取り組みについて、学会として検討すべき時期にあると考えています。
本学会のこれらの役割に対する会員ほか皆様からの期待も様々かと思います。会員・関係者の皆様の声に耳を傾けつつ、第14期の運営委員・準委員の皆様と共に学会の諸活動の継続と発展に努めてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。